
SIPECジャーナル
学部の特徴
「知」を集め活用する力を培う
単に知識を得るだけでなく、自ら課題を発見し、仲間と共有しながら学問的に解決していく能動的な学びを重要視しています。その軸が、1年次の入門セミナーから3・4年次の演習へと続くゼミ。3・4年次の演習は一学生あたり平均7名と少人数です。
本学部で学ぶ専門分野について、様々な角度から触れることによって、その概要を把握します。
また、資料文献の読み方、レポートの書き方、プレゼンテーションやディスカッションの方法など、大学生として必要なスキルを演習形式の能動的な学習によって身につけます。
Profile
国際政治学科
グローバル・ガバナンスコース 2年
竹内 美月 さん
TAKEUCHI, Mizuki
高2で米国のピアノフェスティバルに参加し、音楽の力で国際協力に貢献したいという想いを強く持つ。国際協力に携わるためには、社会に関する幅広い知識が不可欠だと感じ、青山学院大学への進学を決意した。

入門セミナーは、国際政治を学ぶ上での基礎力を身につける「土台」となる授業です。レポート執筆では、自分の主張だけではなく、講義で学んだ理論に基づいて考察することを学び、講義内容への理解が一層深まりました。このプロセスを通じて、学んだことを自らの活動に応用していく力が身についたと感じています。また、プレゼンテーションやディスカッションでは多様な価値観に触れ、異なる視点や新たな気づきを得られる貴重な授業でもありました。
専門的な学びへの導入期間。少人数制のクラスで、1年次に関心をもった分野の教員と連携しながら、専門知識を築きます。研究・プレゼンテーション・ディスカッションなどを通して論理的思考力・表現力を培い、専門的な研究へつなげていきます。
Profile
国際コミュニケーション学科
国際コミュニケーションコース 3年
英保 克郎 さん
ABO, Katsuro
得意分野の英語を活かすため青山学院大学を志望。社会に出るにあたっては、培った英語能力をどう有用スキルとして活用するかが大事だと思い、より実践的な知識を習得できる国際政治経済学部を選択した。
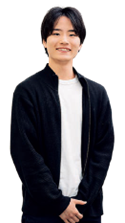
国際政治経済学部では、3年次から2年間かけて論文を書き上げます。大学生活の集大成ともいうべき論文を円滑に進めていく “準備期間”がプリゼミです。データ収集や取材のやり方、テーマ決めなど、難易度の高い作業をステップごとに学んでいきます。教授は学生の自主性を尊重しつつ、個別に丁寧なフィードバックをいただけるので心強いです。また、学生同士のディスカッションは、論文の構成を組み立てる上でとても参考になりました。
学科にこだわることなく個々の学習目標に合わせ自由にゼミ選択が可能です。一学年あたり平均7名の少人数クラスにより、研究発表や討論中心の授業が展開されます。
専門分野を深める過程で、幅広い視野の獲得、論理的思考力、表現力を身につけ、課題解決能力を養うと同時に、将来の方向性を見いだしていきます。また、卒業に向けて、研究テーマを深化させ、演習論文にまとめます。
我々が直面する環境に関する喫緊の課題とその対処法について、
科学的にかつ楽しく論じることを目指しています。
地球温暖化、海洋プラスチックごみ、生物の多様性喪失、化学物質の健康影響など、環境に係わる問題は山積しています。食品ロス問題など身近なものもありますが、温暖化(気候変動)問題にその典型を見るように、環境問題の多くは長期的な視点を必要とするものです。本ゼミではこういった問題を考える基本的な視点(理論)を身に着けるとともに、毎年特定のテーマを決めて議論を進めています。24年度は廃棄物問題、23年度はESG投資と金融の社会的役割について考えました。テーマ選定は学生自身の自主性を重視しています。



Profile
国際経済学科
国際経済政策コース 4年
吉岡 航 さん
YOSHIOKA, Kou
中学高校とハンドボールに打ち込む傍ら、食品ロスにも関心を寄せる。大学では国際政治経済学部の公認学生団体「SANDS(サンズ)」に所属。SDGsの普及活動として、昆虫食をはじめとしたサーキュラーフードを学祭やイベントで販売する取り組みなどに従事。

高校時代から関心を寄せてきた食品ロス。何人もの教授に自分が学びたい分野をアピールし、共感いただいた瀬尾先生のゼミに参加しました。先生主体で進められるゼミが多い中で、瀬尾ゼミは自由度が高く、先生の研究範囲内であればテーマも学生に委ねられます。私がゼミ長になってからは「廃棄物」をテーマに決め、たとえば生き物の死骸や大型の空きビルなど、一見、廃棄物に見えないようなものも取り扱いました。自由な分、有効な学びを得ようと主体的に情報を集める姿勢が養われたと思います。ふと議論で出た単語を拾って繰り広げられる先生の講義も大変興味深いです。卒業論文のテーマは「食品ロスに躍起になる価値はあるのか」。ゼミを通して培った柔軟な思考力を用い、探求の成果として公平な視点で食品ロスを見つめ直すことができました。